軍用オートバイが初めて戦場に姿を現したのは、第一次大戦直前の1911〜1912年のイ
タリア対トルコのリビア戦争であったと言われています。当時は交通手段としての利用が主で、
機械としても未熟なものであったのですが、すぐさま機関銃をすえつけるサイドカーが登場しま
した。
タリア対トルコのリビア戦争であったと言われています。当時は交通手段としての利用が主で、
機械としても未熟なものであったのですが、すぐさま機関銃をすえつけるサイドカーが登場しま
した。
第一次大戦の1914〜1918年の間でドイツ陸軍では、5400台のオートバイ(サイドカーも
含む)が導入されていました。戦後はヴェルサイユ条約で多額の賠償を課せられ、大型兵器の
保有も制限されたので弱小軍に成り下がりましたが、数の劣勢を質でカバーしようと軍の近代
化と研究は継続されていました。
含む)が導入されていました。戦後はヴェルサイユ条約で多額の賠償を課せられ、大型兵器の
保有も制限されたので弱小軍に成り下がりましたが、数の劣勢を質でカバーしようと軍の近代
化と研究は継続されていました。
オートバイも軍用として開発されたものは少なく、民需用をそのまま利用したかシールドや機
関銃を改造して取り付けたものからスタートしており、この辺は軍用車両の発達と重なる特徴
が見られます。当時自動車は非常に高価であり、大量生産システムも完備されていなかった
ので、それを補完する意味合いでオートバイが配備されました。
関銃を改造して取り付けたものからスタートしており、この辺は軍用車両の発達と重なる特徴
が見られます。当時自動車は非常に高価であり、大量生産システムも完備されていなかった
ので、それを補完する意味合いでオートバイが配備されました。

軍用バイク特集を組んであり、現用の陸上自衛隊,第二次大戦のドイツ軍,アメリカ軍,イギ
リス軍が掲載されています。中でも第二次大戦のドイツ軍に紙面を多く割いています。実車の
カラー写真が多く、しかも現存する車両の写真は綺麗です。
リス軍が掲載されています。中でも第二次大戦のドイツ軍に紙面を多く割いています。実車の
カラー写真が多く、しかも現存する車両の写真は綺麗です。
さて、第二次大戦前夜のドイツ軍のオートバイの基準は自動車やトラックのような規則は特
別設けていなかったようで、排気量による区別も行われていませんでした。オートバイメーカー
は、BMW,ツェンダップ,NSU,DKWなどであり、どれも代表的メーカーです。
別設けていなかったようで、排気量による区別も行われていませんでした。オートバイメーカー
は、BMW,ツェンダップ,NSU,DKWなどであり、どれも代表的メーカーです。
DKW社は現在アウトウニオン社となっていますが、1919年設立のメーカーで1930年代のオー
トバイレースで成功を収めています。このメーカーのRT125(後の車両分類の項を参照のこ
と)は、戦後各国の小型オートバイの母体として再生されました。
トバイレースで成功を収めています。このメーカーのRT125(後の車両分類の項を参照のこ
と)は、戦後各国の小型オートバイの母体として再生されました。
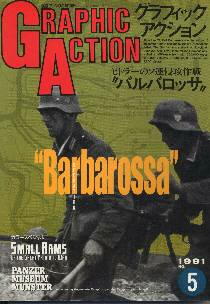
第二次大戦のドイツ軍のオートバイについて、日本語で書かれたものとしては比較的良くまと
まっています。その変遷(第一次大戦から第二次大戦にかけて)について、詳しく記述されてい
ますので、その歴史について知るには第一級の資料と言えるでしょう。
まっています。その変遷(第一次大戦から第二次大戦にかけて)について、詳しく記述されてい
ますので、その歴史について知るには第一級の資料と言えるでしょう。
オートバイの称号としては、”Kraftrad”としていましたが、省略して”Krad”と呼ばれていまし
た。
た。
車種分類
(解説)1938年各種オートバイレースで優勝を飾っていたNZ350を、軍用の偵察用として採
用しました。故障が少なく取り回ししやすいことから兵士達に人気がありました。
用しました。故障が少なく取り回ししやすいことから兵士達に人気がありました。
(解説)『超重量級軍用オートバイ』構想により、BMWのR75と協力して開発されました。最高
時速100kmから歩兵の歩く速度の時速3kmでの走行も可能で、水深45cmの渡河、大きな
登攀力などから、兵士から信頼を込めて「マンモス」や「グルーン・エレファント」との愛称で親し
まれました。
時速100kmから歩兵の歩く速度の時速3kmでの走行も可能で、水深45cmの渡河、大きな
登攀力などから、兵士から信頼を込めて「マンモス」や「グルーン・エレファント」との愛称で親し
まれました。
(解説)第一次大戦後のインフレ対応策として、排気量200cc以下のオートバイは無税にな
り、排気量198ccの民間市販車としてR2が発売されました。その後排気量を二倍にしたの
が、本車でR4としてドイツ軍に採用されました。
り、排気量198ccの民間市販車としてR2が発売されました。その後排気量を二倍にしたの
が、本車でR4としてドイツ軍に採用されました。
(解説)1935年に民間市販車として登場した大排気量車であり、大戦初期のドイツ軍のオート
バイ部隊を支えました。
バイ部隊を支えました。
(解説)R4の馬力を保ちながら排気量を少し減らした車種。
(解説)『超重量級軍用オートバイ』構想により、ツェンダップのKS750と同時に誕生しました。
|
|

